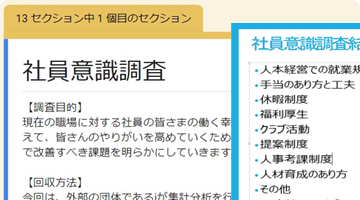第1072号 高齢者という言葉の概念を変えよう
2025.2.17
中小企業の持続可能性をいかに高めていくか、これはわが国産業界において、重要な社会課題となってきています。少子高齢化で15歳~64歳の生産年齢人口が数十年にわたって減少し続ける右肩下がりの環境が中小企業経営の行く手に大きな影を落としているということはこれまで指摘したとおりです。この30年で1300万人も生産年齢人口が減ったので、その分、労働者不足、顧客減少が中小企業を襲っています。減っていく層に選ばれる経営は、その方々に幸せを与えられる幸せ軸の経営に尽きると力説してきました。そして、その具体的な手法として人本経営の実践を強く推奨しています。このことにいささかも揺るぎはしていませんが、少子高齢化ですので、少子ではない高齢化に視点を充てていくことも持続可能性を高めるヒントがあるのではないとかと今週号では論考してみたいと存じます。
高齢者という呼称に対する疑問
令和6年版「高齢者白書」によると「65~74歳人口」は1,615万人と発表されています。30年間で減少した生産年齢人口を補って余りある人口がここにいるのです。この層は、現在、残念なことに高齢者と称されています。
しかし、今年65歳となる有名人を挙げてみると、世界的名優の渡辺謙さん、笑点大喜利司会者の春風亭昇太さん、コメット役を務めた大場久美子さん、そして物まね達者な清水ミチコさんなどまったく高齢者のイメージが湧かない方ばかりです。
また今年、70歳の方も挙げてみると、所ジョージさん、片岡鶴太郎さん、高畑淳子さん、天童よしみさんと現役バリバリです。
さらに74歳の方はというと、神田正輝さん、中村雅俊さん、和田アキ子さん、桃井かおりさんと、これまたまだまだ老け込んでいません。もう高齢者という言い方を変えた方が適切です。
こうした有名人は、いい仕事をしているから元気に見えるという指摘もされそうですが、そこがポイントです。企業内でもこの層が輝くように人事マネジメントをしていくことができたのなら、わが社にもこうした有名人の方のようにイキイキと働く社員を生み出せるのではないでしょうか。これこそが真のタレントマネジメントといいたいものです。
60歳定年などしている場合でない
少なくとも、60歳定年制は即刻廃止して少なくとも70歳以上まで引き上げるか、定年を無くすことを真剣に考えていただきたいのです。今年、60歳すなわち還暦を迎える有名人を挙げるとさらに衝撃的です。チューブの前田亘輝さん、奥田民生さん、本木雅弘さん、女性では中森明菜さん、吉田美和さん(DREAMS COME TRUE)…
企業でこの方々が働いていたら、60歳定年ですと伝えられるでしょうか?
60歳以降の経営人事マネジメントを再考する
今月6日に「『正社員として20年以上勤務した60代』の就労実態調査(パーソル総合研究所)」の結果が発表されました。これによると、「正社員として20年以上勤務した60代前半の就業率は95.8%、60代後半の就労率は89.3%であり、同年代全般を対象にした総務省「労働力調査」(2023年)の74.0%、52.0%よりも著しく高い」と報告されています。
大企業では40歳~50歳代を対象に希望退職を募るニュースが報じられています。例→第一生命HD、希望退職1000人募集 50歳以上が対象
絶対に中小企業ではしてはいけません。この年代の層を正社員として全うに雇用していけば、60歳以降に十分に奉公してくれるのですから。現役時代により大切にされていればいるほど、高齢期になって実に仕事をして会社への貢献、そしてなにより社会への貢献をしている事例を、人本経営の現場では数多くみることができます。高齢者層の雇用を健全に果たしていくことが、持続可能性を高めていくことに直結するということをふまえて今後の経営人事のあり方を今一度考えてみましょう。
このコンテンツの著作権は、株式会社シェアードバリュー・コーポレーション(以下SVC)に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、SVCの許諾が必要です。SVCの許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。